飼育環境:
cages:
飼育ケースは、各種試した。
最も良いのは、天井の低い60cmらんちう水槽に1ペアゆったり飼うと言うスタイル。充分な交尾スペースと夜に徘徊するスペース。運動不足にならなくて長く産卵、長く生きるようだ。
しかし、現実は厳しい。沢山飼いたい、そうするとスペース不足。
それで、妥協の産物として、以下のcase:
400x226xhight190mmのアクリルのパンチ穴ケースに1ペア飼育:
cage;
これが多頭飼育&棚スペースのぎりぎりの大きさ。
babyとか、交配待ちの個体たちは、色の派手なplastic製ケースに収容している。天井が低くて可哀想ではあるが、仕方ない。成体になるとほとんど運動スペースがない。babiesの頃から収容して成長するまで、運動させるのが・・・せめてもの・・・。
plastic;
—-
温度管理:
成体とhatchling(当年生まれ)-幼体では異なる管理。
成体の飼育温度は飼育室の温度としている。
すなわち、5月頃から活動が活発になり、10月をもって活動停止・冬眠になる。
だから冬眠(産卵活動に入らないという意味での)期間は半年6ヶ月ということになる。
その間、餌は入れている。水分の補給も少し乾燥気味に行う。
餌の減り具合を見て冬眠終了とか判断することになる。そうすると水分を十分に補給開始する。
夏の最高室温は、36度とかになる。
冬の最低室温は、夜には数度までなる。
が、常時孵卵器を1つ設定しているので、その上では最低でも10度未満程度。
大切な親カップルは、その上に置いている。
孵卵器は年中点けていて、室温がそれ以下の時は28度摂氏になる。
しかし、当然それ以上では断熱効果があるものの大体それに沿う。
だから、この期間の卵はそのままだと大体死んでいる。
それで卵ケースを人間の活動する部屋に持って歩くことにしている。
我が家人は30度までは耐えられるがそれ以上は冷房するので、人間と一緒だと36度とかにはならないですむ筈。
幼体の管理:
上記親の冬眠期間は、暖房する。と言ってもケースの下に25度とか称するプラ板状のヒーターを置いておく。
1枚/1 case. この場合、餌は常時置いている。
湿度/水分管理:
基本的に、弁当箱製-シェルター1/caseにしている。
この中に個体たちは入るので、水分環境保全になっているはず。
ペアでは、産卵箱を兼ねる。箱の縦幅がケースの横幅いっぱいのプラ製の弁当箱のような物を使う。
蓋をして、ふたの真ん中に45mm四方の入り口を開ける。
その中には、適度な水分を含むvermiculiteを8割程度まで満たす。
親の水分補給はバーミキュライトからと、産卵箱の周りに隔日に水をピペットで垂らす。
ケースの下敷きはコピー用紙の裏(印刷していない方)を上にして敷いている。掃除が簡単。
幼体も同様。
ただし、シェルターになる箱はケースにあわせて小さくして、バーミキュライトは高さの半分程度に減らす。
最初の3ヶ月程度は、ケースの紙の上にバーミキュライトを敷く。
そしてボトル飲み物蓋を置いて、その中に水をピペットで給水。その際、overflowすることもokと。vermiculite の水分補充となる。
その意味は、地上環境の湿度補給になっている筈。
ただし、今住んでいる851-countyは、以前住まいの272-countyより湿度10%以上高い。
それで、関東地方太平洋側などはもっと水分補給した方が良かったような気がしている。
幼体では上記のように・・・冬期にも下から温めるので、水分管理に要注意。時々、乾いて脱皮不全となる。
幼生期の脱皮不全は、いつまでも尾を引いて結局breederとして成熟しないことになることがほとんどだ。
—
—



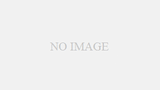
コメント